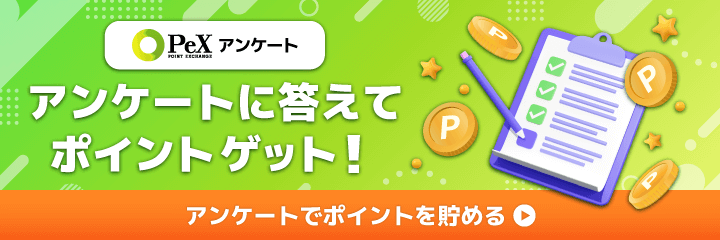事故が“半分以下”に減るのに…「夢の交差点」 なぜ日本では普及しない?
- 乗りものニュース |

欧米では信号機のない環状交差点「ラウンドアバウト」が普及しています。安全性の高さや災害への強さが利点である一方、日本では導入が進んでいるとは言えません。何が課題となっているのでしょうか。
「東日本大震災」を機に導入開始も…
ヨーロッパ地域などの道路では、信号機のない環状交差点「ラウンドアバウト」が普及しています。安全性の高さや災害への強さが利点である一方、日本では2025年現在、導入は進んでいると言えません。何が課題となっているのでしょうか。
 栃木県大田原市に整備された「ラウンドアバウト」の例(画像:国土交通省)
栃木県大田原市に整備された「ラウンドアバウト」の例(画像:国土交通省)
ラウンドアバウトは一般的な十字形状の信号交差点とは異なり、中心部分に設けられた円形の道路を、一方向に周回しながら通行するタイプの交差点です。1970年代以降、ヨーロッパやアメリカで普及し、今では広く一般化しています。
その最大の特徴は、安全性の高さです。構造上、通行する車両は速度を落とさざるを得ないことや、車両同士が交錯する地点が、従来の信号交差点より圧倒的に少ないことが、事故の発生を抑えています。
警察庁の統計によると、ラウンドアバウト導入後の交通事故発生件数は、年間で約6割減少しています。特に死亡・重傷事故については、導入されてから1件も発生していない(2021年度時点)というデータもあります。
また、ラウンドアバウトは信号機を設置しなくても運用できるため、停電が発生しても問題なく通行が可能です。日本では東日本大震災をきっかけに、災害に強いラウンドアバウトを整備するための検討が加速。2014年に道路交通法が改正され、本格的な導入が始まりました。
その一方、日本で整備されたラウンドアバウトの数は、2023年3月末時点で全国155か所。限定的な導入にとどまっているのには、いくつかの原因があります。
そもそも“日本の道路”に向いてない?
まず課題となっているのが用地の確保です。ラウンドアバウトはもともと広い面積を必要とする構造で、トラックやバスなどの大型車が通行することも考慮した場合、環状部分の直径は36m~40mほど必要となります。しかし都市部をはじめ、すでに多くの建物が密集している日本において、このように広大な用地はなかなか取得できません。
 大分県宇佐市の「ラウンドアバウト」(画像:国土交通省)
大分県宇佐市の「ラウンドアバウト」(画像:国土交通省)
また、ラウンドアバウトは許容できる交通容量が低く、キャパシティを超えた際には、効率が一般的な交差点以下まで落ちる欠点があります。国土交通省ではラウンドアバウトの整備条件として、1日の総流入交通量が1万台未満という目安を設けています。ところが日本の都市部では、主要な交差点の多くがこの基準を超過しているため、そもそも導入ができないのです。
さらに日本は欧米に比べ、歩行者や自転車の通行が多いことも問題です。ラウンドアバウトは、車両だけの通行ならばノンストップで通過できますが、横断交通も過密な日本では現実的な運用形態ではありません。
これらの要因から、日本におけるラウンドアバウトの整備事例は、交通量の少ない住宅地などに限られています。数が少ないことから、ドライバーへの通行ルールの周知も進んでおらず、初めて利用したドライバーを混乱させる、悪循環も生んでしまっているのが現状のようです。
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね |  |
|
|---|---|---|
| ムカムカ |  |
|
| 悲しい |  |
|
| ふ〜ん |  |