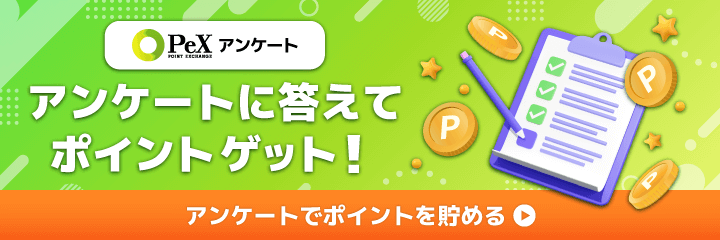鉄道バスの「赤字を補填」←世界はそれを「投資」と言う 消耗するだけの日本の“見方”
- 乗りものニュース |

日本の地方公共交通は「赤字」、そして税金で「補填」が必要と見なされがちですが、世界でそれは「投資」と捉えられています。この視点の違いが、地域経済に大きな差を生んでいる実態を解説します。
公共交通に投資すると5倍のリターン!?
「日本の地域交通は危機どころか、もはや危篤」――これは、鉄道・バス会社の両備グループ、小嶋光信代表の言葉です。コロナ禍後、失った乗客が戻らず地方の公共交通はまさに危篤状態に陥っています。
 赤字鉄道路線の代表例、JR芸備線(画像:写真AC)。
赤字鉄道路線の代表例、JR芸備線(画像:写真AC)。
日本は可住面積あたりの人口が多く、公共交通に適した国土のはずなのですが、なぜこれほどまでに追い詰められているのでしょうか。地方鉄道やバスのニュースが「赤字が続き存続が厳しい」というフレーズで締めくくられ、私たちは公共交通が赤字だと捉えがちです。
しかし、この捉え方は世界から見ると「ファイナンスや経済学がわかっていない」と受け止められるかもしれません。
なぜなら、先進国の多くでは公共交通への資金投入を資本(ストック)に対する「投資」と見ているのに対し、日本では赤字を補填する「費用(フロー)」と捉えているからです。費用として資金を投じてもリターンは得られませんが、投資をすればリターンが得られます。ここに決定的な違いがあるのです。
米国公共交通協会(APTA)のレポートによると、公共交通への1ドルの投資は、地域経済全体に平均5ドルの経済効果(投資対効果500%)をもたらすという分析結果があります。これほどのリターンが出る根拠は、三つの要因にあります。
一つ目は、経済循環効果です。投下された資金が、鉄道やバスの設備投資(インフラ投資)や運行費用(ランニング)として、地域の企業や住民に直接支払われます。このお金が地域で消費され、税収増や地価上昇を生みます。
二つ目は、外部性です。公共交通が移動を促すと、商業・観光が拡大し、高校や大学の選択肢が増えて人口定着を助けるといった地域の競争力が高まり地域社会への効果(正の外部性)をもたらします。また、自動車交通が生み出す公害、事故、渋滞などの社会的費用(負の外部性)を減らす効果もあります。
三つ目は、公共交通には運賃収入があるため、投資額の大部分を利用者から回収でき、実質的な投資額が小さくなるため、投資の5倍ものリターンとなるのです。
ここで大事なのは、投資をしてリターンを得るのは、バス会社や鉄道会社などの運行事業者ではなく地域社会全体である点です。
赤字の「補填」ではリターンなし
欧米の多くの地域では、自治体などが地域経営のツールとして公共交通に投資をし、経済を回し、住民のQOL(生活の質)を引き上げ、人口確保や地価上昇などのリターンを得ています。運行は民営企業が行う場合でも、運行費用は自治体との契約で賄われます。
 英国ポーツマス市のバス。1台のバスが75台の自動車を減らすとアピールしている。グローバルオペレーターであるファーストグループが受託運行(山田和昭撮影)
英国ポーツマス市のバス。1台のバスが75台の自動車を減らすとアピールしている。グローバルオペレーターであるファーストグループが受託運行(山田和昭撮影)
一方、日本の公共交通は民営企業に委ねられ、交通事業が黒字になるように運行します。路線が赤字になって廃止されれば、地域の経済循環はストップし、住民のQOLも下がります。そこで、廃止が進み過ぎないよう、補助金を出して赤字の一部を埋めています。赤字の「補填」なので、出費は少なく済みますが、赤字補填の現状維持では地域の競争力は高まらずリターンは得られません。
経済学者の故宇沢弘文博士は、住民の経済・文化・社会の魅力を豊かに持続させる社会的装置を社会的共通資本と名付け、投資は市場原理だけで判断してはいけないと説きました。これに対し、日本の鉄道・バスは市場で独立採算を求められ、投資不足(市場の失敗)に陥っています。
また、日本の交通市場は公平な競争になっていません。自動車交通の社会的費用は市場価格には反映されず、社会全体で負担していますが、日本の政策ではこれが十分に配慮されていません。道路の建設・維持管理は公費(税金)で行われる一方、鉄道は基本的に運賃収入を元手にします。国の道路予算が約2兆円に対し鉄道予算は約1000億円と20倍もの差があり、投資環境も公平ではないのです。
さらに、インフラ投資の評価手法にも違いがあります。欧米で主流の多基準分析(MCA)は公平性や環境など多面的な価値を評価しますが、MCAは定量化や説明が難しいという側面があります。このため日本の政治的・公共的な議論では、経済効率性を数値で示す費用便益分析(CBA)が「わかりやすい」とされ、主流になっています。
しかし、CBAには欠点があります。一つは、環境価値など市場で取引されない価値を、無理に市場均衡で算定しようとする経済学的な矛盾です。もう一つは、得られた便益が「誰にどれだけ配分されるか」という、地域や年齢層などを踏まえた視点が一切考慮されない点です。評価手法の段階で、公共性や社会的な価値が軽視される構造なのです。
一般道に課金!?
経済学的には、運賃を払う必要がある(=排除性がある)ため公共交通は純粋な公共財ではない、という理論もあります。しかし世界では、社会的な価値を最大化するため、一般道に課金し鉄道を無料にするような、真逆の政策が一部地域で戦略的に実施されています。
2025年1月、ニューヨークのマンハッタン島南部で自動車の通行に課金する混雑料金が導入され、これが渋滞を減らしました。エストニアの首都タリンは、2013年に住民投票の結果を踏まえて公共交通を無料にしたところ、中心街の人口が増加しました。
公共交通への資金投入を単なる「赤字補填」と捉えるとリターンを逃します。地域経済を支え、社会的費用を軽減し、持続可能な社会を維持するため、未来への戦略的な投資とすれば、リターンが得られます。この視点の転換こそが、日本の交通政策を大きく変え、地方の活力を取り戻す鍵となるでしょう。
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね |  |
|
|---|---|---|
| ムカムカ |  |
|
| 悲しい |  |
|
| ふ〜ん |  |