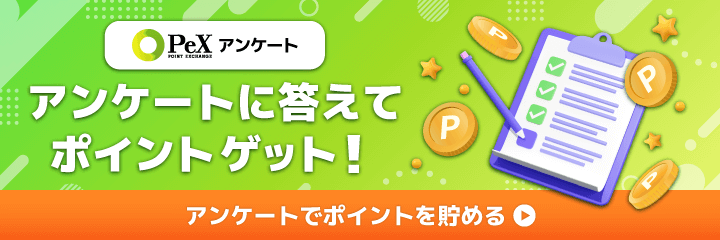バブル絶頂期に描かれた「未来鉄道」は実現したのか “狂気の大風呂敷”の答え合わせ
- 乗りものニュース |

東京の膨張がいつまでも続くと信じられていたバブルの時代に書かれた「21世紀の東京圏の鉄道交通」とは、どのようなものだったのでしょうか。後に実現したものから夢に終わったものまで、当時の論文に記された様々な提言を振り返ります。
成長が続いた未来、東京圏の鉄道はどうなっていた?
昭和の末から平成初頭にかけて日本全土を熱狂させた「バブル景気」。経済循環の観点では1986(昭和61)年12月から1991(平成3)年2月頃の5年間を指しますが、株価は1989(平成元)年末の3万8915円をピークに翌年秋には約4割下落しており、1990(平成2)年初頭にバブルは崩壊したと見るのが一般的です。
 バブル景気の頃にかけて具体化しつつあったつくばエクスプレス(画像:写真AC)
バブル景気の頃にかけて具体化しつつあったつくばエクスプレス(画像:写真AC)
とはいえ好景気の渦中では「これは一過性のものに過ぎない」とは考えないもので、当時の雑誌の記述を見ても「バブル」の用語が登場するのは崩壊直前のこと。少なくない人々が、日本の成長はこれからも続くと信じていたのです。
例えば中銀カプセルタワービル(東京都中央区、2022年解体)や国立新美術館(同・港区)を設計した建築家・黒川紀章氏を含む学識者8人は「グループ2025」を結成し、1987(昭和62)年5月に「昭和100(2025)年」を目標年次とする「東京改造計画の緊急提言」を発表しました。
構想の中核は、土地が足りず、高騰しているのであれば、東京湾に3万ヘクタール、人口500万人規模の「新首都新島」を造成して大量供給しようというもの。東京23区のおよそ半分の面積の島が、東京湾の内陸寄り(今で言えば東京湾アクアラインの内側)にすっぽり収まるイメージです。
この「新首都」を中心に、国道16号や外環道、首都高速中央環状線に沿って地下鉄を建設、また名古屋・京都・大阪と「新・新幹線(リニアモーターカー)」で接続し、世界都市・東京の発展を列島全体に波及させようという、良く言えばロマンあふれる、今となっては狂気のような構想でした。
そんな時代、交通業界はどんな未来像を描いていたのでしょうか。「日本鉄道電気技術協会」が1991年に募集した懸賞論文の入選作品「21世紀の東京圏における鉄道交通」(『鉄道と電気技術』2巻10号)から、その一端を垣間見るとしましょう。
通勤ラッシュを見た外国人の反応が忘れられず
この論文、一執筆者の未来予想と切り捨てられないのは、車両製造から電気設備まで幅広く鉄道事業を展開する日立製作所のシステム事業部輸送システム部長だった安藤正博氏が執筆したものだからです。
安藤氏は戦後の約45年間で「衣」と「食」は欧米先進国と比較しても質・量ともに遜色ないレベルに向上したが、「住」、特に大都市圏での鉄道交通は「欧米先進国の通勤時の混雑レベルと比べて遙かに及ばない」と指摘します。
安藤氏は1986(昭和61)年にカナダで開催された世界交通博覧会で、日本の通勤ラッシュの映像展示を見た先進国の見学者が、驚いた顔をすると同時に、くすくすと笑って立ち去る状態が忘れられないと述べます。
日本人もこれで良いと思っていたわけではありません。1990年度「国民生活白書」の「国民の社会資本への不満度」には、幹線道路の渋滞が50%で1位、続く2位が「大都市圏のJR、私鉄・地下鉄の混雑」の約30%でした。「日本の表玄関である東京圏の鉄道交通問題を解決してこそ、東京は世界に恥ずかしくない国際都市になる」というのが安藤氏の問題意識でした。量から質へ、ゆとりの時代へ、これはバブル崩壊後も一貫して続いた時代の要請でした。
1990年頃の東京圏の混雑率は平均200%で、路線によっては250%を超えていました。混雑は以前から問題になっていましたが、バブル景気で長距離通勤者が増加し、下落傾向だった混雑率が増加に転じた時期でした。鉄道輸送力の増強が求められた反面、地価の高騰で用地取得が困難となり、新線建設が停滞した時代です。
最初の提案は「大深度地下鉄による輸送力の増強」です。駅間距離5km程度の急行路線として表定速度を40~50km/h台にアップ。これを既設路線の地下深くに敷設しようというもので、西武鉄道が1987年に発表した新宿線地下複々線化計画にも通じる発想です。安藤氏は具体化しつつあった常磐新線(つくばエクスプレス)の秋葉原~北千住間に言及していますが、実際にはほぼ通常の地下鉄と変わらない形となりました。
「第2」「第3」の提案、そして24時間運行…実現したのは?
第2がリニアメトロの敷設です。安藤氏はリニアメトロの研究開発でプロジェクトリーダーを務めており、論文の発表直後には東京初の路線として「都営12号線(大江戸線)」光が丘~練馬間が開業しています。急勾配、急曲線の路線計画が可能で、建設費も安いリニアメトロで山手線と武蔵野線の間にもう一つの環状線(メトロセブン、エイトライナー)を建設する提案です。
第3がモノレールの活用です。東京モノレール以降、日本の主流となっているのが「日立アルウェーグ式」であるように、日本のモノレール技術を牽引(けんいん)してきたのが日立です。
安藤氏はモノレールの新たな活用方法として、大深度地下鉄と反対に既設路線の上空に敷設してはどうかと提案します。また、モノレールは各駅停車、既設鉄道線は2階建て車両を複数連結した快速として、着席サービスも拡大します。
これらをあわせて、JR東日本の総武、常磐、東北、中央、東海道の5路線直下の大深度地下鉄建設が約5兆円。リニアメトロの環状線が1.5兆円、大手私鉄各線に併設するモノレール建設が約4.5兆円、合計約11兆円と試算。民間の資金では不可能なので、第3セクター設立や国の補助など公的な支援が必要と記しています。現代のプロジェクトと比較すると、リニア中央新幹線東京~名古屋間の建設費が約7兆円なので、文字通りケタ違いの構想でした。
もう一つ提言しているのは、「世界の中心となる国際都市東京」にふさわしい24時間運行です。ニューヨークは複々線を活用して24時間運行を実現していますが、前述の大深度地下鉄、リニアメトロ、モノレールを複々線として活用すれば、同様のサービスが可能というのです。24時間運行はバブル崩壊後もたびたび議論されましたが、コロナ禍以降は終電繰り上げが進むのが現実です。
重ねて記しますが、これはあくまでも安藤氏が個人として投稿した論文であり、日立の公式見解ではありませんが、交通業界がどのようにバブル景気に向き合ったのかを示す貴重な資料といえるでしょう。
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね |  |
|
|---|---|---|
| ムカムカ |  |
|
| 悲しい |  |
|
| ふ〜ん |  |