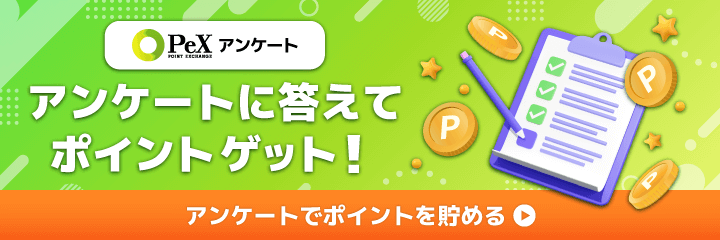「仕事に行きたくない」…連休明けの“メンタル不調”を防ぐには? 憂鬱を乗り越える「3つのヒント」
- オトナンサー |

土日祝日に仕事が休みの人の場合、2025年11月は3連休が2回あります。年末年始や2026年1月10日~同月12日など、12月以降も連休が控えており、気持ちを切り替えるのが大変な人は多いのではないでしょうか。SNS上では、連休最終日や連休後に「会社に行きたくない」「やる気が出ない」といった声が多く上がります。
脳科学や大脳生理学をベースに、プロ野球選手のようなアスリートやビジネスパーソンにメンタルトレーニングを行う脳レボ(神戸市)代表の川谷潤太さんによると、連休明けの心の不調は「甘え」ではなく、心と体からの正直なサインだといいます。連休明けに憂鬱(ゆううつ)になるメカニズムと、憂鬱になるのを防ぐための具体的な対処法について、川谷さんが解説します。
無理に頑張ろうとするのはNG
連休明けに「会社に行きたくない」「やる気が出ない」などのメンタル不調が生じる最大の原因は「非日常から日常への急激な切り替え」にあります。
休暇中は、仕事の責任や評価のプレッシャーから離れ、睡眠や食事、活動量も“休日モード”に最適化されています。そのリラックスした心地よい状態から、仕事や学校という日常へ急に戻ろうとすると、その大きなギャップが心に負担をかけ、エネルギー不足を起こしやすいのです。「五月病」のような状態とメカニズムは似ています。長期の休暇で一旦緊張がほぐれたことで、心の糸がぷつんと切れたように感じてしまうことがあります。
さらに、連休が終わると、「また同じ日常が続く」という漠然とした不安、つまり「未来への期待感の喪失」が、メンタル不調の引き金になることが多くあります。年末年始のように新生活を意識する時期であれば、「今年はうまくやれるだろうか?」という期待と不安が同居し、自己評価のハードルが上がりがちなことも、気分が沈む原因となります。
土日祝日に仕事が休みの人の場合、年末年始や2026年1月10日~12日の連休など、12月以降も連休が続きますが、連休明けの不調を「ただの気分の落ち込み」と軽視して放置してしまうと、不調が一時的なものから慢性化しやすくなります。心のエネルギーが低迷すると、集中力が散漫になり、ミスが増えたり、人間関係でイライラしやすくなったりといった悪循環に陥ります。
心身への影響としては、短期的には睡眠・食欲の乱れ、無気力、集中力低下が目立ちます。中期的には、遅刻や欠勤の増加、仕事のパフォーマンス低下が連鎖し、自己効力感が揺らぎやすくなります。
特に、12月以降は連休が続くため、「連休→仕事→連休→仕事」というサイクルの中で、心が切り替えのタイミングを見失い、より深刻な不調につながる可能性もあります。
次のような症状が見られる場合は、単なる気分の落ち込みではなく、専門的なケアが必要なサインとして、早めに医療機関や専門家への相談を検討しましょう。
【医療機関や専門家に相談する目安】
・職場や学校に行こうとすると涙が出る。
・「消えたい」「死にたい」など、強い否定的感情が頭をよぎる。
・感情が何も湧かない「無」の状態が続く。
連休明けのメンタル不調を防ぐには?
連休明けのメンタル不調を防ぐためには、「頑張らなきゃ」「無理にポジティブになろう」と自分を追い詰めるのは逆効果です。まず大切なのは「今はしんどい」と自分の状態を素直に認めることです。ここでは、心のエネルギーを回復させ、連休明けを軽やかに乗り切るために、具体的に実践できる3つのヒントをご紹介します。
(1)「未来の楽しみ」で今の自分を引っ張る
心のエネルギーが落ちている時、脳は不確実な未来よりも「楽しみな未来」に意識が向いている方が、やる気や活力を生み出しやすくなります。この性質を利用し、「これを叶えるために今日も頑張ろう」と思えるような、ワクワクする予定やリストを日常に組み込むことが重要です。
小学生の頃、「遠足の日の朝はワクワクして早起きしてしまう」なんてことはありませんでしたか。そんな気持ちと重ねて、私は「遠足効果」と呼んでいます。日常のモチベーションを維持するために、次の3つのリストを作成し、毎日視認できる場所(スマホのメモやホワイトボードなど)に置いておくことが効果的です。
・やりたいことリスト
仕事での新しい挑戦や日常で楽しみたいことなど、難しく考えず何でもOKです。
・行きたい場所リスト
「春に京都の桜を見に行く」「夏に北海道旅行を計画する」など、具体的な場所、時期、誰と行くかまで記入するのがお勧めです。
・欲しいものリスト
欲しいものをリストに書いてみましょう。例えば「パソコン」ではなく「MacBook Pro」など、できるだけ具体的に記入してください。
これらのリストを眺めるたびに、日常に戻る意欲が高まり、未来の楽しみが「今」の頑張りを支える原動力となります。
(2)「行動が先、気分は後」で朝のハードルを下げる
心のエネルギーが低調な時、私たちは「元気になったら行動しよう」と考えがちですが、実際には「気分→行動」の順では動きにくいのが特徴です。重要なのは、行動を先に、気分は後からついてくるという原則を適用し、最小の行動でスイッチを入れることです。次のように行動してみてはいかがでしょうか。
・前夜の仕込み(小さなご褒美)
連休最終日や出勤の前夜に、「明日の朝は○○するのが楽しみ」と思える小さな楽しみを用意しておくと、行動のハードルが下がります。例えば、「お気に入りのコーヒー豆を用意しておく」「新しい服やリップを『今日初おろし』にする」「出勤途中に寄る『コンビニの○○』をプチ楽しみにする」などです。
・当日の朝(五感への刺激)
「会社に行くのは無理」と感じた朝は、まずは五感への刺激を一つ入れることから始めます。「窓を開けて空気を入れる」「太陽の光を浴びる」「コップ一杯の水を飲む」「顔や肩をパンパンと刺激する」などです。
・「最低限でOK」戦略
服装やメーク、朝食などは「最低限でOK」というマインドで臨みましょう。完璧を目指さず、外に出られる状態なら100点です。
・“午前だけ”戦略
もし連休明けに1日フルで働くのがしんどい場合、「午前だけ職場に行ってみよう(行ってみてしんどい場合は午後に半休を取ろう)」「1時間だけ様子を見よう」と、ハードルを意図的に下げるのが有効です。動き出すと、意外と流れに乗れるものです。
(3)心身が疲弊したら「誠実な休み」を選択する
心身が疲弊している場合、無理をして悪化させるよりも、休む判断をすることが大切です。休むことは逃避ではなく誠実な行動であり、職場への連絡は責任ある行動です。休む時の対処法は次の通りです。
・連絡手段
電話で職場に連絡するのがつらい場合は、メールやチャットなど、自分にとって楽な方法で連絡をして構いません。
・伝える内容
完璧な説明は不要です。理由や背景を無理に説明せず、「本日、体調がすぐれないため、休ませてください」のように、事実を短く淡々と伝えるだけで十分です。
連休明けの不調は、決して「弱さ」ではありません。無理に気合いで乗り切ろうとせず、「今はそういう時期なんだな」と自分の状態を認めてあげることが、心の回復の第一歩です。紹介した小さな行動を積み重ね、未来の楽しみで今を引っ張る仕組みを作りながら、自分なりのリズムで乗り越えていきましょう。
脳レボ代表 川谷潤太
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね |  |
|
|---|---|---|
| ムカムカ |  |
|
| 悲しい |  |
|
| ふ〜ん |  |