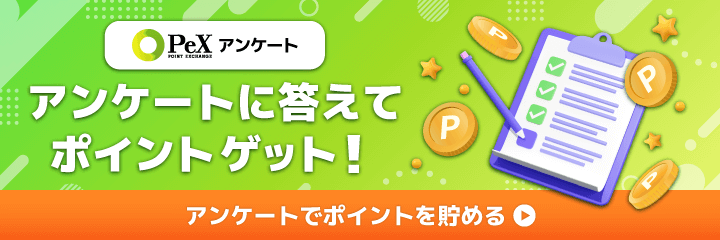「寒暖差」が便秘&下痢引き起こしメンタル不調に!? 専門医が説く「腸内環境」改善に役立つ食べ物
- オトナンサー |

10月下旬以降、急に気温が低くなり、体調を崩してしまった人もいると思います。「気温差が大きい時期は寒暖差により、腸内環境が乱れる」という話をよく聞きますが、本当なのでしょうか。腸内環境の乱れを放置するリスクや、腸内環境を改善する方法などについて、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック(大阪市天王寺区)院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。
腸内環境の乱れが免疫力低下の原因に
Q.寒暖差により、腸内環境が乱れるという話をよく聞きますが、本当なのでしょうか。その場合、どのような症状が出やすいのでしょうか。
安江さん「寒暖差が大きい季節には『おなかの調子が悪い』『便秘や下痢を繰り返す』といった訴えが増えます。これは迷信ではなく、医学的にも説明がつく現象です。気温差が大きくなると、体は体温を維持しようとして自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスを崩しやすくなります。腸の動きや血流は自律神経に大きく影響を受けるため、その乱れが腸内環境にも波及するのです。
交感神経が優位になると腸の動きが抑えられ、便秘のほか、ガスがたまることによるおなかの張りを引き起こします。一方、副交感神経が過剰に働くと腸が活発になり、下痢や腹鳴が起こることもあります。つまり、寒暖差による自律神経の乱れは、腸の運動リズムの乱れとして現れます。また、寒さで血管が収縮すると一時的に腸の血流も低下し、腸の粘膜バリアー機能が弱まり、善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れやすくなります。これが『腸内環境が乱れる』状態です。
腸の環境が乱れると、便通の異常だけでなく、肌荒れや免疫力の低下、疲れやすさ、メンタルの不調など全身に影響します。腸は『第二の脳』とも呼ばれ、脳と自律神経で密接に連携しています。
特に女性やストレスを感じやすい人、冷えやすい体質の人は寒暖差の影響を受けやすく、過敏性腸症候群(IBS)のように症状が長引くこともあります。気温の変化が大きい季節に『何となくおなかの調子が悪い』と感じるのは、体の自然な反応といえます」
Q.寒暖差による腸内環境の乱れを改善するにはどうしたらよいのでしょうか。改善に有効な取り組み、逆効果な取り組みについて、それぞれ教えてください。
安江さん「寒暖差による腸の不調を整えるには、『体を冷やさない』『自律神経を安定させる』『腸内環境を育てる』の3つが基本です。
まず、体を温めることです。冷たい飲み物や生野菜ばかりの食事は一時的に腸の血流を低下させるため、温かいスープやお茶、温野菜を取り入れることが大切です。特に起床直後や就寝前にさゆを飲むと、腸の働きが整いやすくなります。おなかを冷やさないために腹巻きや温かい服装を心掛けることも効果的です。
次に、生活リズムを安定させてください。睡眠不足や食事時間の不規則さは自律神経を乱し、腸の働きを不安定にします。就寝・起床時間を一定に保ち、朝食をしっかり取ることで腸の1日のリズムが整います。また、ウオーキングやストレッチなど軽い運動を1日20〜30分取り入れると、腸の動きが自然に活発になります。
食生活では、発酵食品と食物繊維の組み合わせが鍵です。ヨーグルトや納豆、みそなどの発酵食品は善玉菌を増やし、野菜や海藻、キノコ類に含まれている食物繊維はそのエサとなります。寒暖差によるストレスで腸内細菌のバランスが乱れやすい時期こそ、これらをバランスよく取ることが重要です。
逆に、急な断食や過度な糖質制限は腸内細菌のエサが不足して環境を悪化させる恐れがあります。また、冷たい飲み物やカフェインの過剰摂取は交感神経を刺激し、腸のリズムを乱すことがあります。腸の調子を取り戻すには、極端な方法ではなく、日々の小さな習慣の積み重ねが最も効果的です」
Q.寒暖差による腸内環境の乱れを放置した場合のリスクについて、教えてください。
安江さん「一時的な腸の乱れは自然に回復しますが、長期間放置するとさまざまな悪影響が出てきます。
まず、慢性的な便秘や下痢の原因となります。自律神経のバランスが崩れたままになると、腸の動きをコントロールする神経が過敏になり、過敏性腸症候群に移行することがあります。便通異常や腹部の張りが繰り返されると、日常生活にも支障を来すことがあります。
次に、免疫力が低下します。腸は免疫細胞の約7割が集まる臓器です。腸内環境が乱れると免疫の調整機能がうまく働かず、風邪をひきやすくなったり、アレルギー症状が悪化したりすることがあります。また、腸内の炎症やバリアー機能の低下が続くことで、将来的に脂肪肝や糖尿病などの生活習慣病につながる可能性もあります。
さらに、肌荒れや精神面への影響も無視できません。腸のバリアー機能が低下すると栄養吸収が悪くなり、肌の乾燥や吹き出物、髪のパサつきなどが生じやすくなります。腸と脳は神経でつながっており、腸内細菌の変化はセロトニンなどの神経伝達物質のバランスを乱します。その結果、イライラや不安感、集中力の低下を招くこともあります。
つまり、寒暖差による腸の乱れを軽視せず、早めに生活習慣を整えることが大切です。温かい食事、十分な睡眠、適度な運動を意識することで、腸は本来のリズムを取り戻します。腸をいたわることは、心と体を守ることにもつながります」
オトナンサー編集部
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね |  |
|
|---|---|---|
| ムカムカ |  |
|
| 悲しい |  |
|
| ふ〜ん |  |