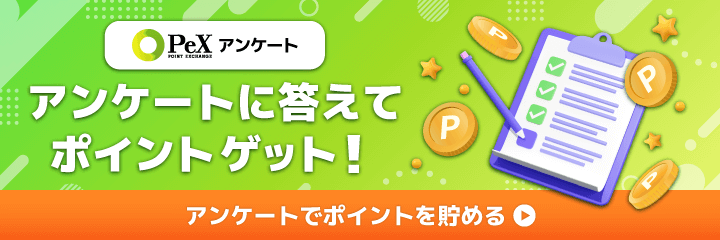たまった「歯垢」が糖尿病、アルツハイマーを引き起こす!? 予防歯科の専門家が教える、今すぐできる“口腔ケア”
- オトナンサー |

11月8日は「いい歯の日」です。「い(1)い(1)歯(8)」の語呂合わせにちなみ、国民に歯や口の健康維持、健康増進を呼び掛けるのを目的に、日本歯科医師会が1993年に制定しました。
近年、歯や歯茎の健康に注目が集まっています。そんな中、歯垢(しこう、デンタルプラーク)が虫歯や歯周病といった口腔(こうくう)トラブルだけでなく、糖尿病や心筋梗塞(こうそく)、アルツハイマー病などの全身疾患を引き起こす可能性があることが近年の研究で明らかになっています。歯垢を放置する危険性や、口内に歯垢がたまりにくくする方法などについて、予防歯科学が専門の大阪大学大学院 歯学研究科 予測歯科創造共同研究講座 特任教授の天野敦雄さんに聞きました。
歯垢の細菌密度は「便」と同レベル
Q.そもそも、歯垢とはどのような物質なのでしょうか。
天野さん「歯垢は、口の中の常在菌とその産生物からなる歯の表面に付着した白く柔らかな沈着物です。食後数時間で形成され、歯垢1ミリグラムの中には1億個以上の細菌が存在していることが知られており、その棲息(せいそく)密度は便に匹敵します。
歯と歯茎の間にできる溝を『歯周ポケット』と言います。健康な状態だと、歯周ポケットの深さは1~2ミリですが、歯垢や歯石がたまると歯茎が炎症を起こし、歯周ポケットが3ミリを超えて深くなります。
例えば、すべての歯に5ミリの歯周ポケットがある場合、手のひらと同じ面積の潰瘍が歯周ポケットの内側にできています。その潰瘍面に細菌の塊である歯垢が密着しているのです。この状態が続くことで、歯周病菌の代表格である PG菌(Porphyromonas gingivalis)などの歯周病菌が潰瘍面から体内に侵入し、糖尿病や心筋梗塞、アルツハイマー病などの全身疾患に影響を及ぼすことが近年の研究で明らかになっています。
さらに歯周病が進行すると 、歯周ポケットの奥には酸素が届きにくくなり、出血した赤血球に含まれる鉄分を栄養にして歯周病菌が一気に増殖。タンパク質を分解する強力な酵素を持つため、歯周組織を破壊し、免疫反応のバランスを崩し、慢性炎症を引き起こします。
この慢性炎症が全身に広がることも動脈硬化や心疾患、脳血管疾患のリスクを高める要因になると考えられています。さらに妊娠中の人の場合、胎盤上皮細胞にPG菌が侵入することで早産の可能性が高まることも報告されています。
厚生労働省(※1)によると、国民の2人に1人が4ミリ以上の歯周ポケットを有する歯周病に罹患、35歳以上85歳未満のう蝕(虫歯)経験者の割合が90%(※2)を超えるなど、多くの人はこうした歯垢によるさまざまな健康弊害を引き起こす危険性、いわゆる『歯垢リスク』を抱えていることが考えられます」
(※1)厚生労働省「歯科口腔保健の推進に向けた取組等について」
(※2)厚生労働省「令和6年歯科疾患実態調査」
Q.歯垢による健康リスクを起こしやすい人の特徴について、教えてください。
天野さん「歯垢が引き起こす健康弊害への危険性、いわゆる『歯垢リスク』の実態を啓発する活動を行う歯垢リスクPR事務局が2025年8月5日~同月6日、全国の10代後半から60代の男女計600人を対象に『歯垢リスク実態調査』を行い、私が同調査を監修しました。
この調査では、『歯みがきにかける時間が短い』『自分の口の臭いが気になる時がある』など全10項目で構成される『歯垢リスクチェックシート』が使われ、5項目以上に該当する場合は『歯垢リスクがある』、2項目以上4項目以下に該当する場合は『歯垢リスクの可能性がある』とそれぞれ診断しています。
調査の結果、全体の8.3%が5項目以上の『歯垢リスクがある』、38.6%が2項目以上4項目以下の『歯垢リスクの可能性がある』にそれぞれ該当し、合計46.9%が『歯垢リスク』を抱えていることが判明しました。
また、『歯垢リスクがある』『歯垢リスクの可能性がある』の合計の割合を性別、年齢別に見ると、50代女性は50.0%、60代女性は56.0%と全体よりも『歯垢リスク』が高いことが分かりました。
こうした背景には、40代以降の女性に訪れるホルモンバランスの変化が関係していると考えられます。特に女性ホルモンの一つであるエストロゲンは女性の免疫力を高めるだけでなく、歯茎の血流や唾液の分泌を助けるなど、口の健康維持に大きな役割を果たしています。
しかし更年期を迎える頃から分泌量が減少し、歯茎の炎症や口の乾燥が起こりやすくなり、歯茎の抵抗力の低下につながります。
さらに近年の研究では、エストロゲンの低下が骨密度だけでなく顎の骨や歯を支える骨の健康にも影響することが報告されており、歯周病のリスクを高める一因ともいわれています」
Q.歯垢を増やしやすい食べ物はありますか。
天野さん「やはり砂糖入りの菓子は歯垢を増やします。意外かもしれませんが、秋の旬の野菜や果物であるサツマイモや栗も、実は歯垢による疾患リスクを高める可能性があります。これらに含まれるでんぷんが唾液によって分解され、糖となり、歯垢を作る大きな要因の一つになるからです。
特にミュータンス菌と呼ばれる虫歯菌はショ糖を主な栄養源として増殖し、歯垢の中で酸を生成します。この酸が歯の表面のエナメル質を溶かすことで、虫歯の発生につながるのです。砂糖入りの甘い菓子だけでなく、自然な甘さを持つサツマイモや栗でも同様のリスクがあるため、食後のケアは欠かせません」
Q.日常生活で歯垢を上手に取り除くにはどうしたらよいのでしょうか。
天野さん「毎日しっかり歯磨きをしているという自信がある人でも歯磨きだけで歯垢を十分に落とし切ることは難しく、磨き残しが多く残る場合があります。歯科医院で歯みがき指導を受けた人でも歯みがきだけで落とせる歯垢は6割程度といわれています。歯磨き指導を受けたことがない人の場合、磨き下ろせる歯垢は2割程度です。多くの歯垢などの汚れが口内に残ったままになっているのです。
先述のように、歯垢1ミリグラム当たりの細菌の棲息数は便に匹敵します。丁寧に磨いているつもりでもプラークが蓄積し、“トイレの後、きちんと拭けていないお尻”のような状態が口の中にあるかもしれないと考え、無理なく正しい方法でセルフケアを続けるのが重要です。
そこで、手軽に取り入れられるケアとして、食後にキシリトール入りのガムをかむことをお勧めします。ガムをかむと唾液の分泌を促して歯垢を付きにくくする効果があり、歯ブラシでは届きにくい部分のケアをサポートしてくれます。
さらに虫歯の原因であるミュータンス菌はキシリトールを食べ物と思って食べます。しかし、キシリトールは消化されないため、細菌は消化作業を延々と続けてしまい、エネルギーを消耗して弱ります。このような状態のミュータンス菌は、酸を出したり歯垢を増やしたりする能力を下げてしまいます。その結果、ミュータンス菌によるう蝕発生リスクを抑えることができるのです。
正しい歯磨きと併せて、キシリトール入りガムのような習慣化しやすいケアを取り入れることが、歯と全身の健康を守る第一歩になります」
オトナンサー編集部
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね |  |
|
|---|---|---|
| ムカムカ |  |
|
| 悲しい |  |
|
| ふ〜ん |  |