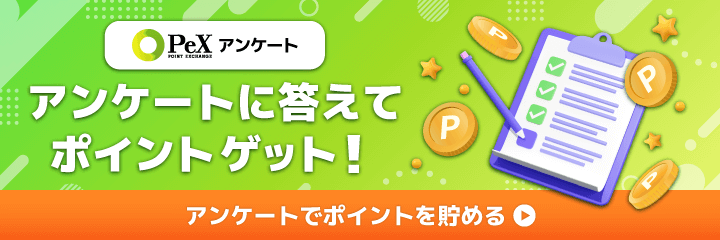「そんな鉄くずどうするんだ」で始まり、今はリピーター続出!? “日本最長の保存鉄道”どうやって維持? 冬はマイナス30度の地
- 乗りものニュース |

りくべつ鉄道は5.7kmの廃線跡を動態保存に活用しています。列車の運転体験は日本最長の距離を誇り、全国からファンが集います。
「誕生前夜」に行われた回送作戦
北海道の北見市から路線バスで南下すること約1時間半、陸別町へと入ります。町はかつて酪農と林業が主産業でした。冬季には氷点下30度前後まで気温が下がり、その過酷な環境を活かした「しばれフェスティバル」や、天文ファンを魅了する町営天文台、ラリー世界選手権も開催されます。様々なイベントがある町に2008年に開業したのが「りくべつ鉄道」です。
 陸別駅舎にはホームが直結されており、車両保管を兼ねた大屋根が車両達を風雨と雪から守っている(吉永陽一撮影)
陸別駅舎にはホームが直結されており、車両保管を兼ねた大屋根が車両達を風雨と雪から守っている(吉永陽一撮影)
りくべつ鉄道は、2006年に廃止となった第三セクター「北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河線」(以下、銀河線)の旧陸別駅から、北へ1駅の旧分線駅までの廃線跡を活用し、列車の動態保存と運転体験が行える施設です。
陸別~分線間は5.7kmもあり、日本一長い区間で動態保存と運転体験ができるとあって、全国から鉄道ファンが訪れ、リピーターも多いです。りくべつ鉄道事務局長の杉本武勝さんに、保存鉄道となった生い立ちから今後の展望までをお聞きしました。
陸別町に鉄道が通ったのは1910(明治43)年のこと。開業時は網走線、その後に網走本線と称して池田~網走間を結びました。石北本線の開業までは、函館や札幌方面と北見・網走を結ぶ唯一の鉄道でしたが、1961(昭和36)年の路線再編によって北見~網走間が石北本線へ編入、池田~北見間が池北線となりました。
国鉄時代に特定地方交通線へ指定され、国鉄分割民営化後はJR池北線となりましたが、1989(平成元)年に銀河線として開業。銀河線は北見市、訓子府町、置戸町、陸別町、足寄町、本別町、池田町の1市6町をまたぎ、総延長140kmと第三セクター鉄道では当時最長を誇りました。
銀河線の経営は当初こそ好調でしたが、不況や沿線の過疎化など複合的要因で経営が悪化。陸別町を含む沿線自治体は廃止に反対していたものの、結果的に廃止が決定されました。
そして、廃止日の2006年4月21日、陸別町では動きがありました。最終列車後の午前0時前、北見、池田、足寄に留置していた6両のCR70形とCR75形気動車を回送し、陸別駅へと集結させたのです。
廃止直前に町へ移送したワケ
鉄道用地は午前0時をもって銀河線が廃止されると市と町へ移管され、1市6町の境界で各自治体の所有となります。自治体をまたいでの輸送は調整や事故時の対応などで困難が予想され、それならばと午前0時前に線路上を回送しました。
 陸別駅は国鉄時代から重厚な跨線橋が活躍してきた。この跨線橋とCR形気動車は銀河線時代からの顔である(吉永陽一撮影)
陸別駅は国鉄時代から重厚な跨線橋が活躍してきた。この跨線橋とCR形気動車は銀河線時代からの顔である(吉永陽一撮影)
なぜ陸別駅へ回送させたのか。それは当時の陸別町長と商工会長が「車両を使って動態保存できないか?」と模索したからです。車両は平成元年車で車齢が18年と若く、まだまだ使えます。車両回送後の約1か月後、旧車庫から車体を持ち上げるリフティングジャッキや、ガラス、ドアといった鉄道部品を陸別駅へと輸送し、動態保存の態勢を整えました。
「そんな鉄くずを持ってきてどうするんだ、と町民から言われたこともありました」
杉本さんは当時を振り返りながら苦笑いをします。動態保存には運転士の確保も課題で、一筋縄でいかないのは予想されました。そこで関係者は各地で動態保存を実施している施設を見学し、町長と商工会が率先して動き、モデルケースとして「碓氷鉄道文化村」などを参考にしました。
りくべつ鉄道の動態保存は、OB運転士による乗車体験だけではなく、鉄道ファンなどの一般人が運転を体験できる施設として2008年に開業しました。開業時は陸別駅1番線が乗車体験用、2番線は運転体験と、駅構内のみでスタート。廃線跡は線路を温存し、廃止から4年後に駅構外から北側へ約1.6kmを整備して延伸しました。
運転体験は駅構外も可能とし、2021年には旧分線駅まで延伸。日本最長の運転体験ができる保存鉄道が誕生しました。
りくべつ鉄道は陸別町の所有であり、敷地は町有地なので鉄道関連の法律は適用されませんが、踏切は廃止されているために道路が優先となります。警察へ道路使用許可を毎月取り、保安要員を配置してから列車通過の対応をします。安全に関しても、運行を支えるスタッフ同士の連絡を密に取り、列車の運行から保守点検まで安全運行を遵守する体制を整え、運転体験を支えています。
気になるのは、5.7kmという長距離の管理です。保守は町内の業者に委託して枕木交換や線路点検を実施し、元国鉄保線区が役員となって点検を管理しています。“日本一寒い町”は冬に氷点下35度まで下がり、寒暖差で地面の隆起が起きますが、線路の歪みは過去にもありませんでした。
杉本さんいわく「網走線の建設時、線路基礎となる部分の地面を深く掘って地慣らしをした」とのことで、現在でも線路保守の上で助かっているようです。
ただし保線体勢が整っていたとしても過信できません。事故を起こさないためにも、運行速度は約15~20km/hと鈍足ですが、その積み重ねが大事なのです。
保存鉄道の「運営資金」どう確保してる?
ところで、保存鉄道は洋の東西問わず、ボランティア運営が基本です。りくべつ鉄道でも、商工会の青年部と女性部、役場職員などが第2・第4土日にボランティア活動の一環で関わっていました。しかし、モチベーション維持はなかなか難しいものです。行政の仕組みとして、町や商工会が立ち上げた保存鉄道といえども、利益は配当できません。
そこで、商工会役員達が出資した有限会社「銀河の森」を興し、運行に関わる者を職員として所属させました。その後は陸別町が街づくり会社「株式会社りくべつ」を設立。鉄道事業部、物産事業部(物産館の運営)、受託事業部(町営コテージの運営)と三つの事業部を立ち上げ、前会社の職員は鉄道事業部へ引き継がれました。
各事業部にマネージャーを配置し、保安要員等はアルバイトとし、町内で雇用を生んでいます。陸別町という一つの自治体で完結して運営できているのです。
とはいえ、保存鉄道は保守管理に莫大な資金がかかります。銀河線の廃線時、運営費として蓄えていた基金は1市6町で分配されました。その分配基金で、例えばバス転換による経費に充当させたり、鉄道施設撤去費用に充てたりします。陸別町ではりくべつ鉄道のためにも使用しました。その分配基金は10年経過すると一般財源化してもよいのですが、陸別町では基金を残し、メンテナンス費用に充当させています。
それには町長や商工会の理解だけでなく、まちづくりとして保存鉄道が必要な要素なのだという町民の理解も大事です。りくべつ鉄道が開業してから来訪者は増え、リピーターも定着しました。鉄道という観光要素が生まれ、町民の理解も進んでいるようです。
今後は新しい車両や廃線跡の延長をするのではなく、後世にわたって廃止時の状態を維持していくのが目標です。車両は大規模修繕を重ねて維持し、線路の状態も今の雰囲気を残す。言うは易く行うは難しで、その状態を維持するためには、継続的な町民の理解と、町をあげての動態保存への取り組みが大切です。
りくべつ鉄道は開業から17年経過しました。廃止時の町長と商工会が車両だけ持ってきて放っておいたら、静態保存となった可能性もありましたが、町をあげて動態保存へ取り組むことで全国各地から来訪者が増え、町内の雇用促進にもつながっています。
課題は運転士の確保です。来訪者の中にも現役やOB運転士がいるといい、新しい人材を求めています。
「車両も線路も最善を尽くして残していきたいです。何せ、我々は素人なので」
杉本さんは笑顔を残し、午後の業務へと急ぎ足で陸別駅舎へと戻っていきました。
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね |  |
|
|---|---|---|
| ムカムカ |  |
|
| 悲しい |  |
|
| ふ〜ん |  |