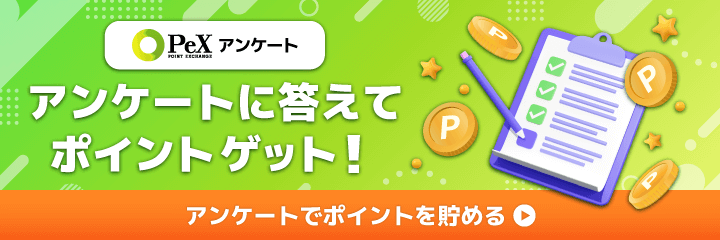お盆期間中、エンドレスで踊り続ける!? 徹夜で楽しむ《日本一ハード》な盆踊りの歴史
- オトナンサー |

全国各地で行われる夏の風物詩といえば「盆踊り」。岐阜県郡上市八幡町では、7月の中旬から9月の初めまで、30夜以上にかけて「郡上おどり(ぐじょうおどり)」が開催されています。お盆期間中には、4日間夜通しで踊りを楽しむ「徹夜おどり」も展開するのが特徴です。
お囃子が翌朝までエンドレスで流れ続ける
郡上おどりは、徳島県の「阿波踊り」、秋田県の「西馬音内盆踊り」と合わせて「日本三大盆踊り」と呼ばれ、2019年には約30万人が来場したことも。2022年には「郡上踊」を含む24都道府県41件の民俗芸能「風流踊」が、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。
郡上八幡は城下町としても知られますが、郡上おどりの発祥は寛永年間(1600年ごろ)にまで遡ります。郡上藩主であった遠藤慶隆が、城下町の整備を進める中で士農工商の融和をはかるため、各所の踊りを城下に集め、盆踊りとして奨励したのが始まりだとか。現在でも郡上おどりの期間中は、市内各所で会場を変えながら開催。一般の人でも自由に輪に入ることができ、櫓(やぐら)を囲ったり、通りを埋めたりする形で踊りの輪が広がります。
通常は午後8時から踊りが始まり、平日・日曜日は午後10時30分に、土曜日は午後11時にお開きとなりますが、8月13~16日の4日間は翌朝4時または5時まで徹夜で開催されます。もちろん途中離脱は可能とはいえ、櫓で演奏されるお囃子(はやし)はエンドレスで流れ続け、止むことはありません。
郡上おどりで演奏されるお囃子は全10曲から成り立っており、落ち着いた歌詞と優雅な所作の「かわさき」、馬の一大産地だった郡上にちなんだ威勢のいい踊りの「春駒」、養蚕の時代にネズミ退治で活躍する猫を模した奔放な型の「猫の子」など、バリエーションに富んでいるのが特徴です。
単調さを避けた唄・お囃子・踊りとなっているため、徹夜おどりでも緩急が常にあり、長時間楽しめるように工夫されています。また、郡上おどりの型はスポーツ科学の観点からも、疲れづらいように構成されていることが学説で証明されているのだとか。また、10曲すべてが国重要無形民俗文化財の指定を受けています。
ちなみに郡上おどり・徹夜おどりは、台風など余程の悪天候でない限り雨天でも開催。雨に打たれても踊り続けるほどの踊り好きのことを、街では「踊り助平」と呼ぶのだそう。祖霊が帰るお盆の夜を、夜通し踊って楽しむのも風流ですね。
オトナンサー編集部
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね |  |
|
|---|---|---|
| ムカムカ |  |
|
| 悲しい |  |
|
| ふ〜ん |  |