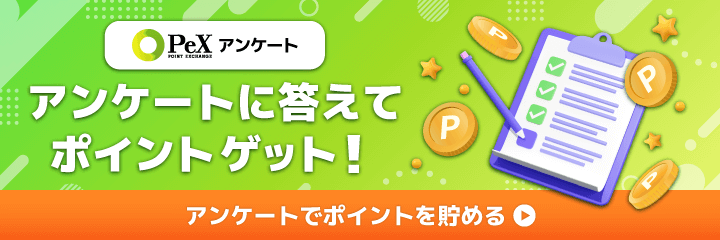長時間労働の人も…「脳卒中」になりやすい人の特徴とは?【専門医に聞く】
- オトナンサー |

10月は「脳卒中月間」です。脳卒中はがん、心疾患、老衰に次ぎ、日本人の死因の4位といわれています。過労の人ほど脳卒中になりやすい印象がありますが、本当なのでしょうか。脳卒中を発症しやすい人の特徴や脳卒中の予防法などについて、「SOグレイスクリニック」(東京都品川区)院長で脳神経外科専門医、医学博士の近藤惣一郎さんに聞きました。
脳卒中は生活習慣病と大きく関係
Q.そもそも、「脳卒中」とは、どのような病気なのでしょうか。
近藤さん「脳卒中とは、『脳梗塞(のうこうそく)』『脳出血』『くも膜下出血』といった脳の血管の病気の総称です。簡単に言うと、脳の血管が詰まるのが脳梗塞、脳の血管が破れるのが脳出血とくも膜下出血です。それぞれ、次のような特徴があります」
(1)脳梗塞
脳の血管が血の塊(血栓)などで詰まり、その先の脳に血液が届かなくなることで、脳細胞が壊死してしまう状態です。動脈硬化や心臓の不整脈(心房細動)などでできた血栓が脳の血管に飛んで詰まることなどが主な原因です。
『突然、手足がまひする』『体のしびれ』『ろれつが回らない』『言葉が出てこない』『視野が欠ける』などの症状が現れます。痛みは伴わないことがほとんどです。脳卒中の中で約7割を占め、最も患者数が多い病気とされています。
(2)脳出血
脳の内部にある細い血管が破れて出血し、脳そのものを破壊したり、圧迫したりする状態です。ほとんどが高血圧によって、長年にわたり血管に負担がかかることが原因です。突然の手足のまひや言語障害、意識障害などが現れます。くも膜下出血のような激しい頭痛は伴わないことが多いですが、出血した場所によっては頭痛を伴うこともあります。脳梗塞と同様、まひや言語障害が主な症状ですが、出血によって症状が急激に悪化することがあります。
(3)くも膜下出血
脳の表面を覆っている「くも膜」の下にある太い血管が破裂して出血し、脳の表面全体に血液が広がってしまう状態です。
多くは「脳動脈瘤(りゅう)」という、脳の血管にできたコブの破裂が主な原因です。高血圧や喫煙、過度の飲酒が発症のリスクを高めるとされています。
今まで経験したことのない、突然の激しい頭痛が典型的な症状で「ハンマーで殴られたような」と表現されるほど強烈な痛みが特徴です。意識障害や吐き気を伴うこともあります。脳卒中の中で死亡率が最も高い病気の一つで、発症後数時間で命を落とす危険があります。
Q.脳卒中は、どのような人が発症しやすいのでしょうか。
近藤さん「脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)は、個人の生活習慣や体質が深く関わる病気です。特定の要因を持つ人は、そうでない人に比べて発症リスクが高まると考えられています。脳卒中になりやすい人の主な特徴は、次の通りです」
(1)基礎疾患(生活習慣病)を持つ人
高血圧や糖尿病、脂質異常症、不整脈は、血管に大きな負担をかけ、動脈硬化を進行させるため、脳卒中の最大のリスク要因となります。
・高血圧
脳の血管に常に高い圧力がかかるため、血管がもろくなり、破れたり詰まったりしやすくなります。特に脳出血やくも膜下出血の最大の原因とされています。
・糖尿病
血管の動脈硬化を進行させ、血液をドロドロにするため、脳梗塞のリスクを著しく高めます。
・脂質異常症(高コレステロール血症)
血液中の悪玉コレステロールが増えることで、血管の壁に脂質がたまり、血管が狭くなる動脈硬化を促進し、脳梗塞の原因となります。
・不整脈(特に心房細動)
心臓が不規則に拍動することで、心臓内に血液のよどみが生じ、血栓ができやすくなります。この血栓が脳に飛んで血管を詰まらせると、重篤な脳梗塞(心原性脳塞栓症)を引き起こすことがあります。
(2)好ましくない生活習慣を持つ人
日々の生活習慣が、脳卒中リスクを直接的に高めます。
・喫煙
タバコに含まれるニコチンなどが、血圧を上げ、動脈硬化を促進します。その結果、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血のリスクを高めます。
・過度の飲酒
大量のアルコール摂取は、高血圧を引き起こし、特に脳出血やくも膜下出血のリスクを急増させます。
・肥満
過体重や肥満は、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の原因となり、間接的に脳卒中のリスクを高めます。
・運動不足
運動不足は、肥満や生活習慣病を招き、血管の健康を損なう要因となります。
・塩分が多い食事
塩分の取り過ぎは、血圧を上げる直接的な原因となり、特に高血圧による脳卒中のリスクを高めます。
(3)その他の特徴
・高齢者
加齢とともに動脈硬化は進行するため、年齢を重ねるほど脳卒中の発症リスクは高まります。
・遺伝的要因(家族歴)
血縁者に脳卒中の患者がいる場合、リスクが高い傾向にあります。特にくも膜下出血では、家族歴が重要なリスク因子とされています。
・過度なストレス
ストレスは自律神経の乱れや血圧上昇を引き起こし、脳卒中の引き金となることがあります。仕事熱心やせっかち、攻撃的といった性格(タイプA行動パターン)もリスクと関連するといわれることがあります。
これらの特徴に複数当てはまる場合は、より注意が必要です。脳卒中の予防には、日頃から生活習慣を見直し、定期的に健康診断を受けることが最も重要です。医師と相談し、血圧や血糖値、コレステロール値を適切に管理することが、発症リスクを大幅に減らすことにつながります。
Q.「過度なストレス」が脳卒中の原因になるとのことですが、長時間労働による過労の人も脳卒中を発症しやすいのでしょうか。
近藤さん「過労と脳卒中の発症には因果関係があるとされています。長時間労働や疲労の蓄積は、脳卒中の主要なリスク要因を高め、発症の引き金になることが医学的に認められています。
特に日本の労働災害(労災)認定基準では、過重な労働が原因で発症した脳・心臓疾患を『過労死』と定義しており、その関連性が公的に認められています。過労が脳卒中のリスクを高める要因は、主に次の通りです」
【過労が脳卒中を引き起こすメカニズム】
(1)睡眠不足と疲労の蓄積
長時間労働は、睡眠不足を招きます。睡眠時間が不足すると、血圧が不安定になり、血管への負担が増加します。また、疲労の蓄積はストレスホルモンを増加させ、免疫機能の低下や血圧上昇を引き起こすため、脳卒中の発症リスクが高まります。
(2)血圧の急上昇
過度のストレスや疲労は、血圧を急上昇させます。これは、特に脳出血やくも膜下出血の引き金となる可能性があります。高血圧は、血管を傷つけ、破れやすくする最大の要因の一つです。
(3)動脈硬化の進行
慢性的な過労状態は、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病を悪化させます。これらの病気は、血管の動脈硬化を急速に進行させ、脳の血管が詰まりやすい状態(脳梗塞)を作り出します。
【労災認定の基準に見る過労と脳卒中の関係】
厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定」では、過労による脳卒中の発症を判断する際の目安として、時間外労働時間を示しています。
・発症前1カ月間に時間外労働が100時間を超える。
・発症前2~6カ月の平均で、1カ月当たり80時間を超える。
これらの時間外労働は、「疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務」として、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと判断される基準となっています。過労は、もともと持っている高血圧などの基礎疾患を悪化させ、脳卒中発症の引き金になることが多いため、日頃から無理のない働き方と十分な休息を確保することが重要です。
オトナンサー編集部
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね |  |
|
|---|---|---|
| ムカムカ |  |
|
| 悲しい |  |
|
| ふ〜ん |  |