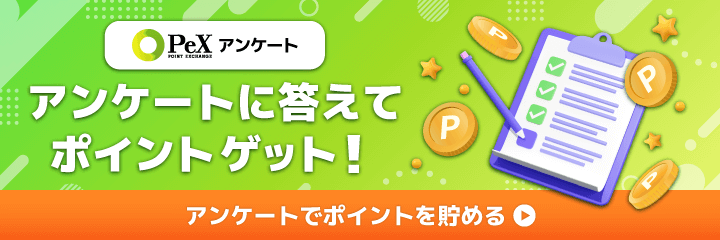大根おろしで259人食中毒…「大根=あたりにくい」は誤り? 専門医に聞いて分かった“まさかの盲点”
- オトナンサー |

大根は年間を通じて手に入る野菜ですが、11月から翌年2月にかけて旬を迎えます。みそ汁の具材に使用したり、自宅で大根おろしを作ったりして食べる人は多いと思います。ところで、愛知県が10月14日、県内の食品加工会社が製造した大根おろしを食べた男女259人が食中毒になり、複数人からノロウイルスが検出されたと発表しました。この件について、SNS上では「大根おろしで食中毒起こることあるんや」「大根おろしで食中毒って珍しくない?」「大根おろしって殺菌作用あるのに」など、疑問の声が多く上がりました。
大根には殺菌作用がある成分が含まれているという話をよく聞きますが、本当なのでしょうか。大根を食べる際の注意点について、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック(大阪市天王寺区)院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。
ノロウイルスには「不活化」の効果なし
Q.そもそも、大根には殺菌作用があると聞きますが、本当なのでしょうか。食中毒を防ぐ効果も含めて教えてください。
安江さん「大根やワサビなどアブラナ科の野菜には、細胞が砕けたときに生成される辛み成分『イソチオシアネート類』が含まれており、試験管レベルでは細菌の増殖を抑える作用(抗菌活性)が確認されています。大根をおろした直後ほど辛みや香りが強いのはこのためです。
ただし、これは“条件付き”の作用で、濃度や温度、接触時間に左右され、食品を無菌化するほどの力はありません。特に冬場に多いノロウイルス食中毒は『ウイルス』であり、辛み成分で確実に不活化できるとは言えません。従って『大根=殺菌食材』だから安全という考えは誤りで、手洗い、器具の洗浄・乾燥、清潔な環境、迅速な冷蔵などの基本的な衛生管理が最重要です。結論は『多少の抗菌活性はあるが、食中毒予防の主役ではない』です」
Q.愛知県が10月14日、県内の食品加工会社が製造した大根おろしを食べた男女259人が食中毒になったと発表しました。実際に大根おろしが原因で食中毒になる事例は多いのでしょうか。
安江さん「件数としては多くありませんが、散発的に発生します。ポイントは“大根そのもの”ではなく、『生で提供される食品』である大根おろしが、調理や製造、盛り付け工程でヒト由来のノロウイルスなどに汚染され、媒介になり得ることです。
ノロウイルスは極めて少量でも感染し、冷蔵庫内では増殖はしないものの長く生存します。ノロウイルスは冷凍でも失活しにくいため、冷凍保存は安全対策にはなりません。外食や加工品で多数の人に同じ食材が配られると、汚染があった場合の影響が一気に拡大します。
つまり『大根おろしだから危険』ではなく、『生提供・大量提供・人の手が多く介在する』ことがリスクです。家庭でも外食でも、作り手の体調管理や丁寧な手洗い、器具の分離・消毒、作り置きや室温放置を避けることが最善の対策になります。下痢や吐き気の症状がある人が大根を加工すると食中毒のリスクが高くなるため、注意してください」
Q.大根おろしを食べる際の注意点について、教えてください。おろした当日のうちにすべて消費した方がよいのでしょうか。それとも、冷蔵保存して翌日に食べても問題はないのでしょうか。また、大根おろしの加工品については、いかがでしょうか。
安江さん「最も安全で風味も良いのは作った当日であり、その日のうちに食べ切ることです。やむを得ず保存するなら、清潔な容器に小分けして速やかに冷蔵(4度以下)し、翌日までに食べるのを目安にしてください。
調理時の注意点ですが、先述のように下痢や吐き気などの症状がある場合は調理を避け、作業前後のせっけんによる手洗い、器具の洗浄・乾燥、まな板やおろし金の生肉・生魚との共有回避が鉄則です。使用する器具は85~90度の熱湯で1分30秒以上消毒するか、塩素濃度200ppmの次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしてください。
室温放置は最長でも2時間以内にとどめ、『黄色や茶色に変色』『粘り・糸引き』『酸臭』などの劣化サインがあれば廃棄してください。加工済みの大根おろしは、表示された要冷蔵温度・消費期限に厳密に従い、開封後は速やかに食べ切りましょう。
なお、冷凍は品質劣化を招き、ノロウイルス対策になりません。安全性を優先するなら、必要量だけ大根をおろし、余らせない工夫がベストです」
Q.このほか、大根おろし以外の方法で大根を食べる際の注意点はありますか。大根は基本的に加熱調理をすれば食中毒になりにくいのでしょうか。
安江さん「何度も強調しますが、サラダや刺し身のつまなど生の状態で大根を食べる際は、調理者の体調管理や手洗い、器具の分離、迅速な冷蔵が基本です。生食である以上、調理工程でウイルスが付けば増えはしなくても生き残るため、衛生管理がすべてと言ってよいでしょう。
一方、煮物やみそ汁、炒め物などの加熱調理は、中心温度が十分に上がればウイルスや多くの細菌リスクを大きく低減できます。一般的に細菌は中心75度で1分以上の加熱、ノロウイルス対策なら中心85〜90度で1分30秒以上の加熱が目安です。
浅漬けや酢の物の調理は“安全化”ではなく風味付けに過ぎないため、衛生管理と冷蔵が必須です。乳幼児や高齢者、基礎疾患がある人には作り立てを優先し、保存品や長時間の常温放置は避けましょう。総括すると、『生食は衛生管理、加熱調理は温度・時間』が安全の要です」
オトナンサー編集部
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね |  |
|
|---|---|---|
| ムカムカ |  |
|
| 悲しい |  |
|
| ふ〜ん |  |