「人生崩壊」「不登校になった」…学校での「いじめ」は“犯罪”じゃないの? 弁護士に聞く“両者の境界線”
- オトナンサー |
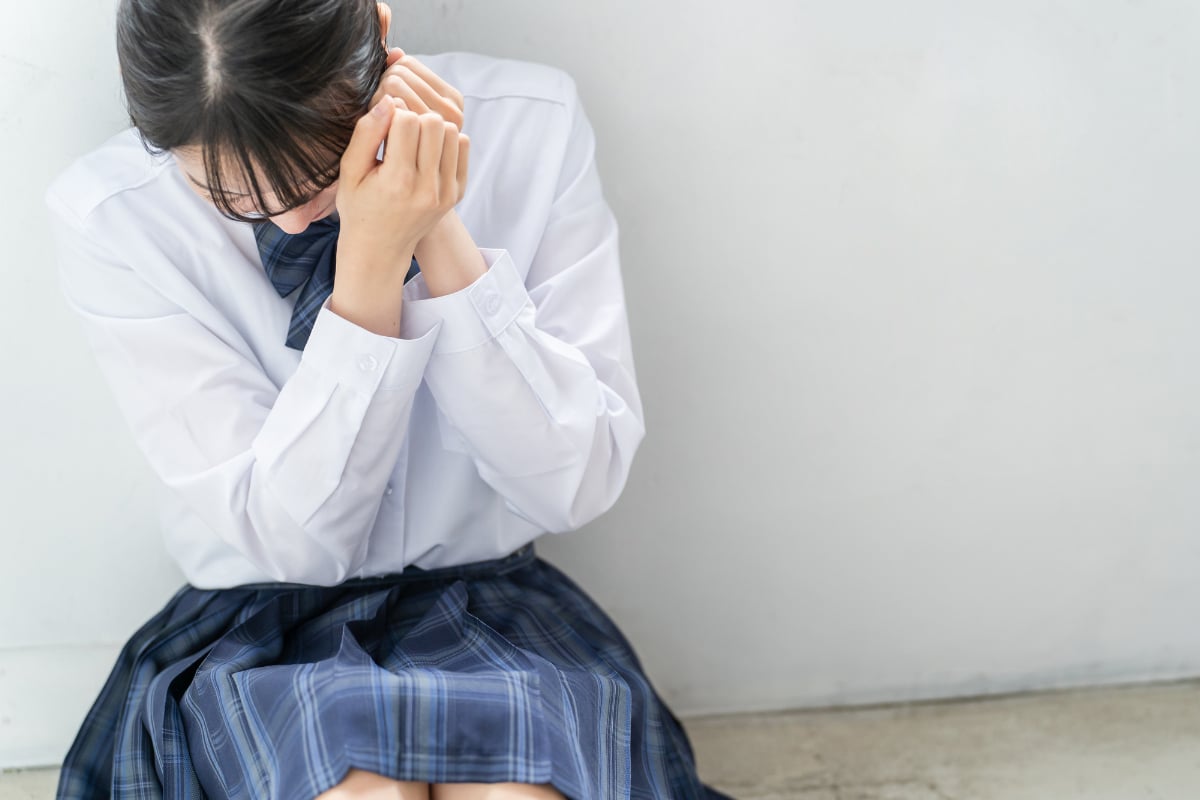
9月になり、多くの学校では新学期を迎えましたが、子どもが同級生や上級生などからのいじめを理由に不登校になるケースは珍しくありません。学校で発生するいじめについて、SNS上では「私も中学のとき、ひどいいじめ受け続けて不登校になった」「いじめは人の人生そのものを崩壊させてしまう」という声のほか、「いじめは立派な犯罪」「いじめという言葉でごまかすな」などの声が上がっています。
そもそも、いじめと犯罪にはどのような違いがあるのでしょうか。両者の境界線について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
法律で「犯罪」と定められた行為に該当するかがポイントに
Q.そもそも、どのような行為がいじめに該当するのでしょうか。法律の観点で教えてください。
佐藤さん「いじめ防止対策推進法は、『この法律において『いじめ』とは、児童など(学校に在籍する児童または生徒)に対して、当該児童などが在籍する学校に在籍しているなど当該児童などと一定の人的関係にある他の児童などが行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童などが心身の苦痛を感じているものをいう』と定義しています(同法2条1項)。
簡単に言うと、いじめ防止対策推進法上の『いじめ』とは、何らかの行為があり、その行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているものすべてが含まれます。
従って『殴る、蹴るなどの暴力行為』や『悪口、からかい』『無視、仲間外れ』『金品をたかる』など、世間が広く『いじめ』だと考えるような、悪意を持ってなされる行為だけでなく、行為者側に悪意がなかったとしても、された側が苦痛を感じれば、『いじめ』に当たると評価される可能性があります。
いじめ防止対策推進法上の『いじめ』があった場合、複数の教職員によって、組織的にいじめを受けた子どもや保護者への支援や、いじめを行った子どもへの指導などを行う必要があります(同法23条3項)。いじめの定義を広く捉えることで、早期に子ども同士のトラブルを発見し、教職員による組織的対応がなされることになり、いじめの悪化を防ぐ効果が期待できます」
Q.テレビや新聞などで悪質ないじめの事案が報じられると、SNS上では「いじめは犯罪」「(犯罪なのに)いじめという言葉でごまかすな」という声が多く上がります。いじめと犯罪にはどのような違いがあるのでしょうか。両者の境界線について、教えてください。
佐藤さん「先述したように、いじめ防止対策推進法上の『いじめ』は非常に広く、さまざまな行為が含まれます。『無視、仲間外れ』は法律上、犯罪には該当しないでしょう。
一方、犯罪とは、法律で犯罪として定められた行為です。例えば、いじめの中でも、殴る、蹴るなどの暴力行為があれば、暴行罪や傷害罪に当たりますし、金品をたかる行為があれば、恐喝罪などに当たる可能性があります。先述のいじめ防止対策推進法23条6項では、『学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するもの』と定められています。
実際に、学校内で子ども同士でなされた行為であったとしても、犯罪行為に当たる場合、14歳以上であれば刑法41条に基づき、刑事責任を問われることもあり得ます。
犯罪として取り扱われるかどうかは、行為者が『いじめ』だと思っていたか、『犯罪』だと思っていたかは関係ありません。法律で定められた犯罪行為に当たる行為をすれば、犯罪として取り扱われる可能性があります」
Q.過去に学校でいじめを受けた人が、退学後や卒業後などに加害者に対して裁判を起こすケースがあります。その場合、裁判で損害賠償の請求が認められる可能性は低いのでしょうか。また、いじめに関する損害賠償の請求権について、時効はあるのでしょうか。
佐藤さん「いじめを受けた人が、加害者に対して裁判を起こす場合、『いじめ』という不法行為により、心身に損害が生じたとして、民事上の損害賠償責任を問うことになるでしょう。
裁判で不法行為と認められるかどうかは、事案によって異なります。不法行為に基づく損害賠償請求権が認められるのは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、これによって損害が発生したと認められた場合になります(民法709条)。先述のいじめ防止対策推進法上の『いじめ』に当たるからといって、不法行為に基づく損害賠償請求が認められるとは限りません。
民事訴訟では、訴える側(原告)が、権利侵害行為(いじめ)があったことなどを立証しなければならないため、実際に、損害賠償請求が認められるかどうかは、過去のいじめを立証するに足る証拠がどれほどあるかにもかかってきます。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、『被害者が損害および加害者を知ったときから3年間』『不法行為のときから20年間』行使しないと、時効によって消滅します(民法724条)。暴力型のいじめの場合は、『人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権』に当たり、『被害者が損害および加害者を知ったときから5年間』『不法行為のときから20年間』行使しないと、時効によって消滅します(民法724条の2)。
従って、いじめの加害者が分かっている場合、不法行為に基づく損害賠償責任を追及したいのであれば、3年以内または5年以内に訴訟を提起するなど行動を起こす必要があります」
子どもがいじめを受けた場合はどう対処すればよい?
Q.学校の部活動では上級生が下級生をいじめるケースのように、いじめが起きやすい印象があります。なぜ部活動ではいじめが生じやすいのでしょうか。実際に子どもがいじめを受けた場合、親はどのように対処すればよいのでしょうか。
佐藤さん「部活動では、子どもが自主的に入部し、お互いに熱意を持って活動するため、部員同士の人間関係が密になりやすい面があります。また、上級生と下級生の間で、明確な上下関係が存在することもあります。こうした背景がある中で、部員同士のぶつかり合いが起こり、いじめの起こりやすさにつながっているともいえるでしょう。
さらに、部活動中、顧問が常に見守っているわけではなかったり、顧問の力が強く、部外の教職員の目が届きにくかったりする中、大人の目が及ばないところで、いじめがエスカレートしていく恐れもあります。
子どもがいじめを受け、保護者に訴えてきた場合、保護者はまず子どもの話によく耳を傾け、事実を聴き取るとともに、子どもの気持ちを受け止めることが大切です。その上で、まずは身近な学校の先生に相談しましょう。いじめに関する相談があった場合、学校は、いじめ防止対策推進法上、組織的対応が求められており、複数の教職員が関わりながら、事実確認やいじめの認知、支援、指導などを進める必要があります。
学校に相談したけれど、十分な対応をしてくれない場合、学校外の教育委員会や弁護士などに相談してみましょう。弁護士が学校交渉を行うことで事態が改善することもあります」
オトナンサー編集部
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね |  |
|
|---|---|---|
| ムカムカ |  |
|
| 悲しい |  |
|
| ふ〜ん |  |



