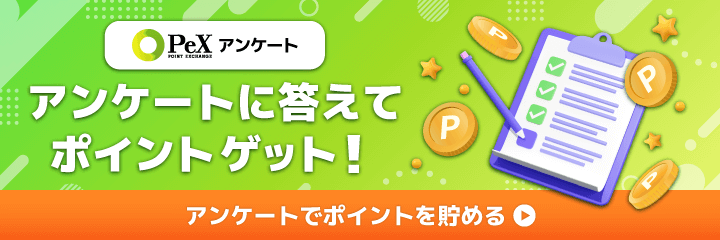季節の変わり目によく起きる「寒暖差アレルギー」とは? 耳鼻科医に聞く発症のメカニズム&予防法
- オトナンサー |

朝晩は涼しくなりましたが、日中はいまだに気温が高い日もあります。秋は日中と朝晩とで寒暖差が大きい時期でもあり、体調を崩しやすいため注意が必要です。ところで、秋は気温差が大きいせいか、SNS上では「鼻水とくしゃみ止まらん。寒暖差アレルギー?」「寒暖差アレルギーがつらい」「寒暖差アレルギーと風邪の違いが分からない」などの声が上がっています。
そもそも「寒暖差アレルギー」という言葉は、どのような症状を指すのでしょうか。主な症状や予防法などについて、わしお耳鼻咽喉科(兵庫県西宮市)の鷲尾有司(わしお・ゆうし)院長に聞きました。
「寒暖差過敏症」と考えると分かりやすい
Q.寒暖差アレルギーとはどのようなものなのでしょうか。寒暖差アレルギーが起きる原因も含めて、教えてください。
鷲尾さん「そもそも、アレルギーは原則として抗原(アレルゲン)抗体反応によるものを指します。アレルギーの診断で最もよく行われているアレルギー検査は血液検査であり、その血液検査は抗原抗体反応を起こす抗体の有無を調べています。血液検査で抗体を確認できれば、反応を起こす可能性(アレルギーの可能性)があると分かります。
しかし、寒暖差はアレルギー物質、すなわち抗原ではないため、血液検査で調べることはできません。寒暖差による反応は、アレルギー反応ではありません。
では、寒暖差アレルギーとは何でしょう。寒暖差はアレルギー物質(アレルゲン)という特異的刺激物質ではなく、寒暖差という非特異的刺激物質によって引き起こされます。非特異的刺激物質とは誰にでも刺激になる物質であり、少ない刺激でも反応してしまうのは過敏症となります。
一方で、アレルゲンのような特異的刺激は、そのアレルゲンに対してアレルギー反応が起こるものであり、アレルギー反応が起こらない人はアレルゲンにさらされる量が多くなっても反応しません。
つまり、寒暖差アレルギーはアレルギー反応ではなく、アレルギーとよく似たアレルギー様反応になります。寒暖差過敏症と言った方が誤解は少ないかもしれません。黄砂やPM2.5、化学物質など、さまざまな刺激物質の一つが寒暖差ということです。刺激物質はアレルゲンと違って影響が大きくなると、どんな人にも症状が出てきます。
寒暖差によって誰にでも起こる自律神経への影響が起こりやすい人、症状が強く出る人が寒暖差アレルギーと表現されているわけです。中でも、よくある症状は鼻の症状で、くしゃみや水っぽい鼻水、鼻詰まりです。また皮膚のかゆみといった皮膚症状や目のかゆみなども生じやすいです」
Q.では、寒暖差アレルギーを発症しやすい人の具体的な特徴について、教えてください。
鷲尾さん「寒暖差アレルギーかどうかを診断する方法はありませんが、ダニアレルギーやスギ花粉症のようにアレルギー性鼻炎の診断がしっかりついている人は、寒暖差アレルギーがあると思っておいた方が良いでしょう。室温や気温の変化によって鼻症状や目の症状、皮膚症状があれば、アレルギーを疑って治療を行い、効果が出れば、医師は治療的診断によって寒暖差アレルギーと判断します。
簡単にまとめると、鼻や喉、肌が弱い人は寒暖差アレルギーに注意が必要です。例えば黄砂やPM2.5、エアコンに弱いなど、寒暖差以外にもアレルギー様反応が出やすい人は過敏症が疑われるということであり、寒暖差アレルギーに気を付けた方が良い人になります。
さらに、花粉症やダニアレルギーなどのアレルギー性鼻炎、ぜんそくやアトピー性皮膚炎、食物アレルギーなど、アレルギー症状が出やすい体質の人はアレルゲン以外の刺激物にも反応性しやすいため、寒暖差による影響が出やすいと言えます。
アレルギーがなく、寒暖差アレルギーによる鼻の症状は『血管運動性鼻炎』といい、アレルギーがある人の寒暖差アレルギーは、アレルギー性鼻炎の非特異的刺激による反応となります」
Q.寒暖差アレルギーと風邪、花粉症は症状が似ていると思います。これらを見分ける方法はありますか。
鷲尾さん「アレルギー症状もアレルギー様症状も、症状的には同じであり、見分け方は特にありません。また、風邪症状は感染症の症状のため、アレルギー症状と同じで、侵入してきた異物(風邪の場合はウイルスや細菌)を除外するといった免疫反応です。
そういう意味で、風邪とアレルギーは基本的に同じ症状となります。寒暖差アレルギーも風邪も花粉症も同じで、防御反応がくしゃみや鼻水、鼻詰まりといった症状として現れます。ウイルスによって起こる反応を風邪、花粉によって起こる反応を花粉症、寒暖差によって起こる反応を寒暖差アレルギーといったように、症状を引き起こす原因が異なるだけであり、基本的には症状に差はありません。
しかし、それぞれに異なる症状の場合もあり、特徴的な症状が出れば、鑑別のきっかけになるかもしれません。例えば、花粉症や寒暖差アレルギーの場合、微熱が出ることがあっても高熱が出ることは基本的にありません。また、花粉症の人が風邪をひいた場合を除き、皮膚のかゆみや目のかゆみといった症状は風邪をひいたときには出ません。
一般的に症状が出始めた初期には、鼻や喉の症状では区別ができないと思ってください。しかし、経過によって見分けることができる場合はあります。風邪とは『原因がはっきりしていないけど、長引いたり繰り返したりせずに良くなれば良し』という意味であるため、同様の症状が長く続いたり、繰り返して続いたりするようであれば、少なくとも風邪ではありませんし、どんな環境で症状が出るかが推測できれば、花粉症も区別できるかもしれません」
寒暖差アレルギーの予防法は?
Q.寒暖差アレルギーの予防法はありますか。
鷲尾さん「寒暖差アレルギーの対策には、寒暖差という刺激に対して強くなる方法と刺激を少なくする方法の2種類があります。
刺激に対して強くなる方法とは、まずアレルギーがあるかどうかによって変わります。先述の話の内容と重なりますが、アレルギー体質が疑われる人はアレルギーの診断と治療が効果的です。可能であれば、アレルギーの専門医の診療を受けるのがお勧めです。アレルギー治療の中に寒暖差アレルギー対策も含まれるため、しっかりとアレルギーに対する治療をしましょう。
刺激に対して強くなるもう一つの方法は体調管理です。花粉症の人なども同様ですが、アレルギー体質ではない人でも、睡眠不足などの体調不良でアレルギー様反応が出やすかったり、ひどくなりやすかったりします。十分な栄養や睡眠、休息を取ることは自律神経を整えて寒暖差に対応しやすい体になる、すなわち刺激に強くなる方法となります。
次に刺激を少なくする方法です。まず、アレルギー体質の人の場合はアレルギーの原因物質であるアレルゲンを少なくすることです。先述のように、アレルギー体質とはいろいろな刺激に対して過敏であるということで、特異的刺激(アレルゲン)と非特異的刺激(寒暖差など)の両方の対策が必要となります。そのためには診断がしっかりついていることが大切です。診断がついていれば、アレルゲン対策もしやすくなり、予防につながります。
また、非特異的な刺激である寒暖差を少なくするには、外気温や室温に応じて、温度変化に対応できる服装を選んだり、マスクをしたり外したりすることが有効でしょう」
オトナンサー編集部
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね |  |
|
|---|---|---|
| ムカムカ |  |
|
| 悲しい |  |
|
| ふ〜ん |  |